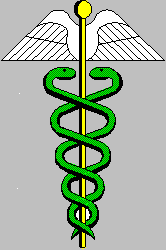プロフェッショナルドクターへのFAQ
Professionai Doctor QandA

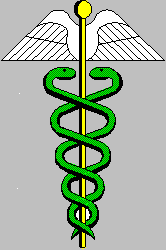
プロフェッショナルドクターは20世紀から電子カルテが使用されていた証です。
しかし、開発以来、10年近く経過しましたので、古いユーザーの先生方にはデータの蓄積によるパフォーマンスの低下が問題になってきました。
そこで、2004年から、世界中でもっとも使用されているフリーのSQLデータベースであるMySQLをエンジンとするMyProdocがプロフェッショナルドクターファミリーに加わりました。
今後は、知恵を使って、各種フリーソフトを集めて、院内データベースシステムを構築する時代です。
このQandAはプロフェッショナルドクター時代のもので、古い記述内容もありますが、ファイルデータベースを使用する
プロフェッショナルドクターに関する疑問は殆ど、網羅されています。
高速電子カルテMyProdocに関してはMyProdocQandAをご参照ください。
(プリントアウトしてお読みください)
ホームページに戻る
製品のラインナップ
資料請求
★質問のインデックス(クリックした項目がトップに表示されます)
ホームページに戻る
★質問と答え★
(問い)プロフェッショナルドクターを開発した会社はどんな会社ですか?
(答え)ノーバメデイコはコンピュータをもっと医療に活用したいと考える医師が集まって札幌で設立し運営する会社です。”医師自身が医師のために必要で役に立つシステムを開発・供給する”という医師同士の相互扶助的な役割の必要性を強調し、実践する会社です。
一言で言えば”医師が必要とするソフトは医学・医療に素人の技術者が作るより医師自身が作ったほうがいいものが安くできる”というわけです。手始めに1995年から電子カルテレセプトシステムの販売を開始しました。今後電子カルテ以外にもいろいろな医療向けソフトその他を開発・販売していきます。
(戻る)
(問い)電子カルテでの処理の流れの概略を教えてください
(答え)概略は以下のとおりですが、①~⑪まですべてコンピュータ画面上での処理になります。
① 受付で患者の受付をします。受付画面を開き、登録された患者の名前を選択することにより受け付けが終了します。
② 新患の場合は新患登録・受付を行います。
↓
③ 診察室ではドクターは診察画面を開きます。
④ 診察画面には受付がすんだ患者の名前が表示されます。
⑤ 画面上で患者名を選んでカルテを開きます。
⑥ 処方・注射・検査オーダーをプルダウンメニューから入力します。
⑦ 患者の所見その他はキーボードからあるいはプルダウンメニューから入力することもできます。
⑧ 診察が終了したら診察画面に診察終了のチェックを入れておきます。
↓
⑨ 受付では診察終了のチェックが入った患者のカルテを開きます。
⑩ 自動入力ボタンをクリックすると再診料・外来管理加算などの医療事務上の項目が入力されます。
⑪ ついで会計計算ボタンをクリックすると、会計計算の結果が表示されますので、前回の未納金・保険外金額などを確認の上、領収書のデータを入力します。
⑫ 院内処方であれば調剤を行って薬剤と印刷した領収書を領収額と引き換えに渡して一連の処理が終了します。
⑬ 院外処方であれば印刷した処方箋を領収額と引き換えに渡して処理が終了します。
⑭ 会計が終了したら会計終了チェックを入れておきます。
(戻る)
(問い)プロフェッショナルドクターはどのようなところが他の医事システムと違うのですか?
(答え)プロフェッショナルドクターは最初から電子カルテとして生まれたために、カルテの入力と医療事務上の処理を自然な形で統合したところがもっとも特徴的で優れている点です。たとえば、医療事務上では内服薬剤の端数処理がもっとも問題で、これをレセプト上で解決するために従来いろいろな工夫がなされていました。しかし、これが面倒なために約束処方の登録・入力が煩雑になり、カルテに書くように自由に追加・削除することのできないようなソフトも実際にあります。プロフェッショナルドクターは処方薬剤をどのようにランダムに入力しても自動的に端数処理をしてくれます。約束処方も自由に登録ができますし、約束処方で入力した薬剤も自由に追加削除することができます。したがって、カルテを記載するのも従来のカルテ同様に自由な感覚でできるのです。
また電子カルテとしての機能が充実しており、患者さんの検査データのグラフ化、薬剤情報の表示・印刷など電子カルテならではの機能がいっぱいです。
またもう一つの特徴は、プロフェッショナルドクターは電子カルテですが、入力したデータから会計事務を処理したり、レセプトを発行したりなどいわゆるレセコン機能をフルに持っているということです。
電子カルテが医療事務・レセプトの発行を自身で処理できずレセコンに依存するようなものであれば無意味であり、コスト的にも無駄です。なぜなら会計事務やレセプト印刷などはデータベースのデータからの単純な演算出力・レポート出力に過ぎないからです。単純な出力を数百万円もするレセコンに依存する必要はありません。
それはたとえていいますと、パソコンのワープロソフトに入力した文章をそのまま印刷できずに、改めてワープロ専用機にファイルを読み込ませないとプリントアウトできない、というようなものです。
このようにプロフェッショナルドクターの持つ、”無駄な時間・無駄な金銭・無駄な労力を省く”という明確なコンセプトと合理的なシステムが全国の若いドクターに広く支持されている理由です。
(戻る)
(問い)プロフェッショナルドクターが商品として優れている点は何ですか?
(答え)
①もっとも歴史のある電子カルテなのでいわゆる枯れたシステムとして安定していること
②直感的な使いやすさを追求したソフトなのでくせがなく導入してすぐに使えること
③買い取りソフトなので一度購入したら永久に使えること
④もっともポピュラーなデータベースソフトであるACCESSでできているので、改造が簡単に自分でできること
⑤ユーザーにはソースが公開されているのでいろいろな機能を自分で付け加えて使用できること
⑥固定のメンテナンス費がないので維持費がかからないこと
⑦データが大量になったときにC/S版にアップサイズする道が開かれていること
⑧自分で改造できるので制度の変更などに対してバージョンアップに頼らずに自分で対応することも可能なこと
⑨ユーザーが多いので情報が入りやすいこと
⑩リースで購入してもリース期間終了後も改訂版を5万円で購入できるなど長期的にみてコストがかからないこと
もっとも重要なことはプロフェッショナルドクターではすべてがオープンであることです。
データベースのテーブルの構造・ソフトウエアのソース・データそのもの、などユーザーにはすべてオープンにされています。したがって従来のレセコンのように自分のところのデータでありながらレセコンから取り出せないということもありませんし、ソフトの変更をしたいときにできないということもありません。ソフトを乗り換えたければデータを移植すればよいのです。すべてはドクターの立場に立って開発・販売されていることの顕われです。医療機関やドクターによってやりたいことは異なります。そのために自由に改造できるようになっています。ソフトのコードやSQLも簡単なものから高度なものまでいろいろみることができます。電子カルテのデータをもとに、会計計算をしたりレセプトに出力したりという一連の過程がすべてオープンにされているのですからこれを参考にご自分で電子カルテを新しく別のツールで構築したいドクターのための参考になるかもしれません。
プロフェッショナルドクターはこのようなソフトです。
(戻る)
(問い)プロフェッショナルドクターがレセプトを作る時はどのようにするのですか、レセコンにデータを送ってレセコンから印刷するのか、それともプロフェッショナルドクターがレセプトを作成する機能があるのですか?
(答え)プロフェッショナルドクターはカルテシステムで編集されたデータをレセプトデータとして独自にレセプトを印刷する機能を持っています。その機能がなければ電子カルテとしてのプロフェッショナルドクターの価値は半減します。電子カルテはあくまでもカルテですから、カルテとして自然な入力ができることが必要条件です。しかし、レセプトはカルテとして入力された内容から、1枚のレセプト上にデータを表現する必要があります。そのために、カルテに入力されたデータをもとにレセプトデータを作成します。データの作成に要する時間はレセプト100枚につき数十秒、500枚で1、2分程度です。レセプトはウインドウズ上のオブジェクトとして印刷され、連続用紙ではなく単票の白紙に書式付きで印刷します。ですからあらかじめ書式を印刷したレセプト用紙などは不要です。プロフェッショナルドクターではさまざまな帳票の印刷が可能ですが、そのすべてであらかじめ書式を印刷しておく必要はありません。
(戻る)
(問い)プロフェッショナルドクターではレセプト印刷が簡単にできると聞きましたが具体的な手順はどうなっていますか?
(答え)レセプト作成システムを起動し、レセプト作成準備画面でレセプト作成の期間を入力し、ボタンを押すとレセプトデータが作成されますのでそのまま印刷するか、あるいは点検画面から患者ごとに診療内容・病名などを点検して印刷します。まとめて印刷したり、患者ごとに選択して印刷することもできます。
(戻る)
(問い)現在マックのレセプトソフトを使用しているが、処理が遅くて会計に患者が並んでしまう。プロフェッショナルドクターのパフォーマンスはどうなのか。
(答え)プロフェッショナルドクターは受付けでのカルテ作成は瞬時、医療事務内容の自動入力のための処理時間が5秒、会計での領収書発行は自動計算に2秒、プリンタが印刷した領収書を出すまでに10数秒の速さで処理します。実際に1日の外来患者が300名という病院並みの施設でもスムーズに稼動しています。プロフェッショナルドクターは実によく働く賢いシステムなのです。
(戻る)
(問い)会計計算がすんだ後で薬の変更などがあったときに、会計の入力をやり直すことが簡単にできますか?
(答え)診療内容にどのような変更があってもカルテの内容に応じた計算をプロフェッショナルドクターが自動的にしてくれますので、再度領収書画面を開き、再度会計領収額を変更するだけですみます。
(戻る)
(問い)自宅や出先から電子カルテを開いて患者の情報を取り出したりすることはできますか?
(答え)電子カルテを導入すると、自宅からクリニックのコンピュータを呼び出して電子カルテを開き、患者の情報をみたり、データを入力したり、あるいは休日にクリニックのプロフェッショナルドクターにアクセスしてレセプト作成の準備をしておき、翌日クリニックで短時間にレセプトを印刷を終了してしまう、というようなこともできます。その他にも在宅医療の患者宅で携帯電話を使用して電子カルテから患者の検査結果を表示させる、その場で診察結果を入力するなどいろいろな応用が可能です。在宅医療での応用については現在プロフェッショナルドクターやその他の付随するシステムを利用して実際にやっておられる施設があります。在宅医療だけでなくグループ診療のような場合にも広く応用できます。
(戻る)
(問い)入院にも対応していますか?
(答え)もちろん入院にも対応しています。入院カルテを外来で開いたり、外来カルテを病棟で開くこともできます。
(戻る)
(問い)病院用はありますか?
(答え)プロフェッショナルドクターは病院用としてもお使いいただけます。ベッド数150程度以上の場合は、来年完成予定(時期未定)の当社のパッケージソフト”ProfessionalDoctor 21 For Hospital”の導入をお勧めします。
(戻る)
(問い)入力はどのようにするのか、自分はキーボードが苦手だから、何かほかの方法があったら教えて欲しい。
(答え)プロフェッショナルドクターは診療項目、処方、検査指示、注射指示はプルダウンメニューからの選択による入力で、診療項目は自動入力もできます。一番肝心な診察の記録はキーボードからの入力またはプルダウンメニューからの入力です。プルダウンメニューはあらかじめ入力された患者の症状、所見をマウスで選択することにより、自動的にカルテに入力されるというものです。かぜのような単純な項目の入力にはなかなか便利です。ただ、思ったようなことをすべて選択するためにはかなり大量の項目をあらかじめ用意しておく必要があります。また今後音声入力も可能になるでしょう。
(戻る)
(問い)音声入力は実用的になっていますか?
(答え)最新の音声入力ソフトは実用的に使用可能です。
プロフェッショナルドクター・MyProdocともに対応しています。
(戻る)
(戻る)
(問い)患者の処方の検索はできますか?また、薬から患者を検索できますか?
(答え)患者に投与した薬の内容はカルテ画面から処方参照ボタンで一括して表示することができます。また、薬剤名から、その薬を投与している患者名を表示することもできます。以前は薬剤名からの検索機能はなかったのですが、ある先生からお問い合わせがあり、そのような機能も必要かもしれないということで追加したものです。
(戻る)
(問い)受付画面で初受診というのはどのようなときチェックするのですか?
(答え)初受診というのは初診ではなく、貴院に初めて来院した患者という意味です。患者登録名簿に今回初めて入力する患者と考えれば良いと思います。患者がどのくらいのペースで増えているのかを検討するときには有用でしょう。また、少し詳しく所見をとる必要があるとか、まず尿検査などを済ませておくなど各医療機関での対応があるでしょうから、それに役に立つようにしたものです。
(戻る)
(問い)プロフェッショナルドクターでは必ずLANを構築しないと運用できないのですか?
(答え)もちろんそのようなことはありません。もともと医療事務ソフトは単に受付・会計処理やレセプト印刷業務を行うだけであれば格別LANを構築する必要はありません。紙のカルテをみながら診療内容を入力すればよいだけですから受付に1台コンピュータがあればそれですむわけです。しかし、電子カルテレセプトシステムでは医療事務を遂行することだけが主眼ではなく、カルテ内容をコンピュータ上でデータベース化することにより院内業務全体を合理化することが目的です。診療内容がデータベース化されればそれに付随して会計事務やレセプトができるようになりますし、医療事務以外の診療情報もコンピュータで加工可能な存在になります。そのために医師は従来紙のカルテに記載していた内容をコンピュータ上のカルテに入力するわけです。受け付けでは再度会計処理をします。そのように各部門で入力された電子カルテのデータをもとにレセプトを印刷することも当然できます。それだけではなく、たとえば患者の住所のようなデータを処理して診療圏を分析するなどのさまざまな統計的分析的処理がごく短時間のうちに可能になるのです。
同じデータにいろいろの部門から入力を可能にするために院内LANが必要になります。つまりは電子カルテレセプトシステムでは医療事務だけを処理するためのものではなく全診療データを記録するという目的のものですからLANが必要になります。大は小を兼ねますから、プロフェッショナルドクターを単に医療事務だけ処理させるために使用するのであれば、電子カルテとして使用せずに、医療事務に必要な項目だけを入力して単体のコンピュータ上で使用すれば良いわけです。
(戻る)
(問い)診察室と受け付けで別々に画面を開いて別の作業をすることはできますか?
(答え)プロフェッショナルドクターはマルチユーザー対応の電子カルテですからもちろんできます。院内ネットワークを構築する目的はまさに各部署で同時進行で連携作業を行うためです。
(戻る)
(問い)100BASE-Tと10BASE-Tではどちらがいいですか
(答え)最近100BASE-TのLANカードを使用しておられるプロフェッショナルドクターユーザーも増えてきました。100BASE-Tではデータ転送速度が100Mbpsで10BASEよりも10倍速くなりますので、ネットワーク上のリモートコンピュータにあるドライブもローカルコンピュータ内のドライブのような感覚で高速に使用することができます。ただHUBの値段がまだ少し高い難点がありますが、数年前に比べると安くなりましたので、今後LANを構築される場合は100BASE-Tをお勧めします。
(戻る)
(問い)会社が小さいと、あとでメンテナンスをちゃんとしてくれるのかどうか不安です
(答え)プロフェッショナルドクターを開発したノーバメデイコは若手医師が集まっている会社です。”ソフトウエアは実際に使う人が作るとき、もっとも優れたものができる”という理念のもとに、医師が自分達で使うためのソフトを作っています。そのため他のどの会社よりもメンテナンスには熱心だということもいえます。何しろ自分達が日々使っているソフトですから。
医学や保険診療の知識がない技術者が医師の希望を聞き取りをして作ったようなソフトであれば、どうしても医師の希望や気持ちを100%表現したものにはなりえないでしょう。やはり医学や保険診療に関する知識を持った医師が直接作ることが必要ですしメンテナンスについても信頼が置けます。
プロフェッショナルドクターはドクターの気持ちにもっとも近い電子カルテシステムであることが受け入れられて、現在広く普及し続けています。また,開発者の独善に陥らないようにユーザーであるドクターのご要望・ご意見・アドバイスを取り入れて常に進化を続けています。そのためユーザーの先生が独自に作成されたオブジェクトをそのまま取り入れさせていただくということもあります。
そのような会社を今後も大きく発展させていただくのはユーザーであるドクターの力です。ドクターの支持のもとでのみプロフェッショナルドクターもノーバメデイコも発展することができます。なによりノーバメデイコは若い開業の先生方を支援するために必要なソフトを開発し安く販売するために生まれた会社であることを強調したいと思います。
(戻る)
(問い)レセコン会社の人から、パソコンベースの医事ソフトは支払基金からクレームをつけられ、結局レセコンを購入せざるを得なくなることがある、と聞いたがそんなことはありませんか?
(問い)その医事ソフトがレセプトに要求される書式・表示データに十分に対応できず、医事ソフトとして使えないようなものであれば結局レセコンを購入せざるを得なくなることはあるかも知れません。そのような事情で消えていったソフトもあるようです。プロフェッショナルドクターは要求されるレセプト表示に100%対応していますのでレセプトシステムとして使えないということはまったくありませんので、ご安心ください。
プロフェッショナルドクターは保険医である医師集団が運営する会社で開発・販売している電子カルテであり、発売以来3年が経過し、すでに数百人のドクターがカスタマイズしたりなど御自分のシステムとして使用されている定評あるソフトです。おそらく電子カルテとして最大数のユーザーを擁しており、医事システムとしても一大勢力を形成しつつあるといってもよいでしょう。
医師同士の相互扶助をモットーとする会社としましても、レセプト内容などに関して何らかの疑義・問題等があればただちに直接厚生省・社会保険庁・社会保険支払基金本部・都道府県医師会・保険医会等に照会して解決を心がけています。
どのような組織であろうと、”医師が医師のために開発したシステムを医師自身が使用すること”にクレームをつけることなどできようはずはありません。
上述のレセコン会社の社員の話はおそらくパソコンベースの医事ソフトに押され気味のレセコン会社の危機感から出た営業トークだと思いますが、レセコンでなくパソコンベースの医事ソフトを使用することそのものがクレームの対象になるということが他のソフトについて事実としてもしあるとしますと、由々しき問題です。支払側とレセコン業界の癒着を意味し、医師としての立場からも放置できない問題と考えられるからです。もしそのようなことを体験・御見聞された場合はご一報ください。
2002年現在、レセコンのシェアは減少し続け、パソコンベースの電子カルテや医事ソフトが普及しています.
(戻る)
(問い)システムのメンテナンスはどのようにするのですか?会社が遠方にあるとメンテナンスの面で不安です。
(答え)おそらくレセコン使用中点数改定の場合や制度の変更の場合などにレセコン会社の保守要員がやってきてメンテナンスをやっていた状況を考えてのご質問だと思いますが、パソコンはブラックボックスではありませんので、専門のメンテナンス要員は必要ありません。今やあらゆる業務をパソコンで処理することが可能な時代に、ファイルをコピー上書きするだけで済むことをいちいち保守要員を呼ばなければならないとしたらこれほど時間的・金銭的に不経済なことはありません。簡単なことをユーザーにさせず、レセコン会社のメンテナンス要員しかできないようなシステムのもとで医師側は高いメンテナンス料を払わされていたというのが今までの状況ではないでしょうか。プロフェッショナルドクターはそのような状況を是正したいと思います。
パソコンベースということは誰にでもできるということです。医療機関そのものもレセコン時代からの発想を切り替える必要があるのではないでしょうか。
診療報酬制度・点数の改正があったときのメンテナンスは御希望の方にCD-ROMでお送りすることにしています。診療報酬点数の改正時には御自分で点数を変更するなどの作業は簡単に可能です。制度の変更などによりバージョンアップされたプロフェッショナルドクターはアプリケーションファイルのみを新しいフォルダーにコピー上書きするだけで従来のデータはそのままで使用することができます。つまり各医療機関での固有のデータは独立したデータベースファイルとして存在しており、保険制度の改定などでシステムの変更が必要になったとしても入れ替えるのはアプリケーションファイルのみをコピー上書きするだけで終了します。また保険点数が変更になった場合もマスターのデータベースファイルを同じように置き換えるだけですみます。このようにプロフェッショナルドクターは最初からメンテナンスが簡単に済むように設計されています。
通常システムを変更する必要がある場合は約5万円程度でバージョンアップしています。
プロフェッショナルドクターは一つ一つの部品の集合から成立してますので、保険制度の改定があった場合、ノーバメデイコでアプリケーションの中身を改造するのは部品の新規作成・交換だけですみ、1、2日の作業ですんでいます。
プロフェッショナルドクターに限らず医事システム全般にとって問題なのは改定にかかる時間ではなく、制度の改定時に新しい制度の具体的な取り扱いの細目が決定されていないということです。これは厚生省の問題です。
(戻る)
(問い)サポート体制は?
(答え)インストール・環境設定・運用・カスタマイズなどシステム上の問題、医療保険上の問題、あるいはハード、ネットワークの問題についてもご質問・ご相談を直接電話でお受けする安心できる体勢をとっています。サポート時間は午前10~午後1時,午後3時~午後6時です(祝日土日は休業)
MyProdocは365日サポート体制です。
(戻る)
(問い)点数改定時に新点数ファイル発送の時期はいつ頃ですか?
(答え)今までの実績ですと、2週間前頃に発送しています。98年の場合ですと4月1日から新しい点数のもとで診療したわけですが、3月20日までに発送しています。
なお、現在マスターやシステムのファイルはホームページ上からユーザーがダウンロードできるようになっています。
(戻る)
問い)プロフェッショナルドクターには電子カルテとしてのどのような機能がありますか?
(答え)プロフェッショナルドクターは窓口会計処理・レセプト印刷などレセコンのもつ医療事務処理機能をフルに持っていますし、また在庫管理機能、スケジュール管理機能などのほかに、メインとなる電子カルテとしての多岐にわたる機能をもっています。
いろいろな電子カルテとしての機能を備えていますが、特に有用な機能を挙げてみましょう。
(1)薬剤データベースとして処方薬剤のデータをカルテ上で表示する。
(2)処方薬剤のデータを患者用に印刷する。
(3)検査結果を自動的にグラフ表示・印刷する
(4)画像データベースとしてあらゆる患者のデイジタル情報を保存する(たとえば内視鏡のビデオを患者のカルテ上で再現するなど)事ができる。
(5)カルテをマウスをクリックしていくだけで入力できる。しかも入力する文章は自由に追加削除して自分の診療スタイルに合ったものにすることができる。一方キーボードからの入力も自由にできる。
(6)約束処方・約束検査・約束注射など自由に登録・入力(約束処方などでの点数の登録は不要)でき、約束入力からの入力を削除・追加することも自由にできる。
(7)患者の説明用や医師自身のために各種のデイジタル情報(たとえば各種X線写真・ビデオ・心雑音などの音声情報・たとえば皮膚疾患などのデイジタル画像・説明用の各種絵やシェーマなど)を無制限に登録することができる。それらの情報をカルテ上で再現することができる。
プロフェッショナルドクターの機能の特徴として、データがお仕着せのものではなく、常にユーザー自身が必要に応じて追加・削除することができる柔軟性があるということです。これらの機能はユーザーである先生方の御要望を吟味して標準仕様の中に取り入れられてきたものです。
(戻る)
(問い)画像のデータベースをパソコン上で扱いたいのだが、プロフェッショナルドクターで可能ですか?
(答え)プロフェッショナルドクターのデフォルトの機能として、画像に限らずすべてのデイジタル情報をシステム内の共通のデータとして無制限に登録することができます。これは絵・シェーマ・X-線写真・エコー、内視鏡などのビデオ・写真・音声情報などをその種類に関わらず自由に登録し、カルテから呼び出すことができるものです。患者のムンテラ、説明用、あるいはドクター自身のための参照用などとして使用することができます。しかもOLEによるリンクをするだけですので、システムのハードデイスクを圧迫しません。またそれとは別に患者のデイジタル情報を患者自身のカルテに保存することももちろんできますので、正常の像を登録しておいて患者のものと比較するなどということが簡単に可能です。
(戻る)
(問い)画像のデイジタル化は面倒ではありませんか?
(答え)画像のデイジタル化は
面倒です。
このご質問は電子カルテでは画像情報もデイジタル化しないとシステムそのものが運用できないと思っておられる方からのご質問ですが、もちろんそんなことはありません。プロフェッショナルドクターでは画像情報をデータベース化して電子カルテ上で表示したり編集したりすることができますが、このような機能を持っていることと、それを実際に利用することとは別問題です。画像のデイジタル化が面倒であればデイジタル画像情報を電子カルテ上で利用しなければ良いだけのことです。
本論の患者画像情報のデイジタル化については, X線写真にしろビデオにしろ現在のところアナログ情報として出力されるものがほとんどですのでこれをデイジタル化することは必要です。ビデオはビデオボードからの取り込みの後編集が必要です。
(戻る)
(問い)もらった紹介状などはスキャナーで取り込むのですか?
(答え)電子カルテは省力化のための手段であり、電子カルテを運用することそのものが目的ではありません。紹介状が最初から電子メールのようにデジタルファイルとしてもらえるのであれば話しは別ですが、手書きの紹介状をスキャナーで取り込んでそれをどうするのかという視点で考えますと、デジタル化するのに手間がかかるだけで、省力化には役に立ちそうもありません。ほとんどのカルテ内容はデジタル化することで医療機関の重複した無駄な処理をなくすることができるので、たとえば処方内容を電子カルテに入力することは大きな意味がありますが、もらった紹介状は1度読んで保存するだけで、それをデジタル化したから意味があるものではありません。手書きの紹介状をそのままデジタルファイルにするなどはリソースを消費するだけです。カルテに紹介状の要旨を記録すればよいのではないでしょうか。なお、紹介状のような医療情報をインターネットなどを介して送受信するには暗号化を徹底する必要があると思います。
(戻る)
(問い)患者に説明するための薬剤情報などはありますか
(答え)受付画面から患者名を選んで薬剤情報ボタンをクリックするだけでその患者に処方された薬剤の作用・副作用情報を印刷することができます。それをもとに説明することもそのまま手渡すこともできます。
(戻る)
(問い)日報、月報はでますか?
(答え)患者別集計、保険区分別集計、未収金集計が日報としても、任意の期間を区切っても出すことができます。
(戻る)
(問い)カルテはやはり印刷しておく必要がありますか?
(答え)99年5月までは、カルテは印刷して押印して保存するということになっていましたので、印刷して保存する必要がありました。しかし、99年に厚生省が通達を出し、デジタル画像ファイルと同様にカルテのデータも磁気媒体での保存を認めました。一定の条件を満たす保存法によれば紙に印刷して保存しなくともよいとするものです。現在のところこの条件を満たすにはCD-Rによる書き込み保存が必要と思われます。プロフェッショナルドクターのユーザーもCD-Rで保存しているという方が非常に増えてきました。CD-Rで保存しないのならば今まで通り紙のカルテに印刷することが必要です。その場合は患者さんの診療が終了したらそのたびに印刷しておくことをお勧めします。もちろんまとめて印刷することもできますので、その場合は紙の量を少なくすることもできます。会計終了の都度印刷しているという施設も多いようです。
(戻る)
(問い)カルテを印刷するときに前回のカルテの次の空白部分に印刷することはできますか?
(答え)できないことではありませんが、人間の手間がかかりすぎて現実的ではありません。プロフェッショナルドクターの現在のカルテ印刷設定を変更した上で、患者の前回の印刷されたカルテを持ってきて、プリンタにセットし、印刷したらまた別の患者のカルテについて同じことをする、ということになります。
このようなことをしていたらそれだけで日が暮れてしまいます。紙を節約したいのであればまとめて裏表印刷をするというのも一つの方法です。電子カルテはカルテをきれいに印刷して保存することが目的ではなく、また紙を節約することが目的でもなく、人間の労力を節約するというのが大きな目的の一つですから、本末転倒の結果になってしまっては意味がありません。紙のカルテはあくまでも法律上の問題をクリアするため印刷・保存するのであり、印刷したカルテを日常診療で使用することはありません。極端に言いますと、紙のカルテは印刷しっぱなし、保管しっぱなしでいいのです。ですからノーバメデイコでは基本的には紙が無駄になっても毎回印刷するということをお勧めしています。電子カルテのデータをCD-Rで保存する場合には紙に印刷することは不要です。
また、MyProdocでは過去のデータの修正・変更・削除・追加のすべてが記録されますので、カルテの印刷は不要です。
(戻る)
(問い)カルテの頭書きなどはどうなっていますか?
(答え)カルテの頭書きは白紙に書式付きで印刷します。またカルテの点数表、カルテそのものも白紙に印刷します。書式をあらかじめ印刷したカルテ用紙・院外処方箋・レセプト用紙などは必要ありません。レセプト用紙やカルテ、各種書類などは通常のPPC用紙、あるいは再生紙などを使用することが多いようです。
(戻る)
(問い)カルテの点数表の印刷はどのようにするのですか?
(答え)レセプトを印刷するときにその月の受診患者分を自動的に一括して印刷することができます。
(戻る)
(問い)ハードを用意する上で注意する点はありますか
(答え)プロフェッショナルドクターは患者の診療データを含むいくつかのデータベースファイルで構成されています。データベースは必ずデータの量が増加していきます。
はじめ十分な性能を持っていたコンピューターでも次第に速度が遅くなっていきます。
パソコンは製品の入れ替わりのサイクルが速いために最初から中級機を選ぶとあっという間に陳腐化します。また以前の状況と異なり性能に対する価格差も大きな違いがなくなりました。
そこで、パソコンの選定に迷うようであれば、その時のハイエンドマシンを購入してください。
もし全体のコストを安く上げたいという方針がハッキリしていれば、自作するかあるいはショップブランドのものを購入するという選択肢もあります。自作あるいはショップブランドの場合は互換CPUを使ったり、不必要なソフトが入っていないので非常に安く導入できます。最近では10万円で十分高機能のコンピュータが入手できます。
ハードデイスクは適切な容量というのはありません。容量が大きければ大きいほど良いでしょう。最近では6Gb以上あるものが多いようです。
メモリは多めに備えてください(最近では128Mb程度以上)。入れようとするメモリーの2倍を入れればあとで後悔することが少ないようです。2~3年経ったら、より高性能なマシンが出ていますので、古いものはもう使いたくなくなるということもあります。その時は新しいマシンを診察室に導入し、古いものは受付用のパソコンに配置替えをするという方法で診察室のコンピューターを最先端のマシンにすると常に快適に仕事ができます。
なお、ハードはWindows NT、2000、XPWindows(98・ME) が稼動するパソコンであれば何処のメーカーのものでも結構です。
ただし、パソコン使用の初心者の場合はすべてのパソコンをパソコン販売店などが自作するAT互換機(ショップブランド)で統一するのは止めたほうが良いでしょう。というのはいくらパソコン販売店が組み立てるといっても構成する部品の組み合せ・設定が100%適切であるとはいえないことがあるからです。また何らかの問題が発生したときにすべてが自作機ですと対照となるコンピュータがない場合に問題を切り分けることができなくなります。もちろんご自分で組み立てたパソコンであれば問題ありません。自分で作ったもの以上に確かなものはないといえるからです。
プリンタは出たばかりの新製品はドライバに不備があることがあります。特にCanon製はドライバに問題があることが多いようです。
なお、SQLデータベースであるMyProdocの場合は、データ量が何百Gigaバイトになろうが、日常業務の処理速度に問題が出ることはありません。
LANボードはあらかじめそのハードに適合しているものかどうかを確認する必要があります。
(戻る)
(問い)ハードに関して現時点での推奨するスペックがありますか?
(答え)現時点(平成16年12月)ではCPUは1GHz以上、メモリー256Mb以上、ハードデイスク100Gb以上をお勧めします。
(戻る)
(問い)サーバーとしていわゆるサーバー仕様機が必要ですか?
(答え)業務で使用するのですから電源やハードデイスクを冗長化したコンピュータが望ましいのは当然ですが、コストの問題もあり、おいそれとはサーバー仕様機を導入することはできません。コンピュータ自体が新しく高性能のものが次々と市場に投入されていますので、サーバー機がすぐに陳腐化してしまうということも問題です。サーバー仕様機の導入を考えるのなら、むしろ市販の高性能パソコンをサ-バ-としてRAIDシステムを導入して外付けにしておき、一つのコンピュータがダウンしてもすぐに他のコンピュータに接続して業務を継続できるようにするほうが現実的かもしれません。
MyProdocの場合は、強力なSQLデータベース版ですので、サーバー仕様機をご用意ください。
(戻る)
(問い)無停電電源装置はサーバー機にだけつけておけばいいですか?
(答え)無停電電源装置は各コンピュータごとに1台必要です。
クライアントコンピュータからデータを入力中にクライアイントコンピュータが停電などにより電源が落ちたとしますと、サーバー機のデータに書き込み中にネットワーク接続が突然切断されることになります。この時サーバーのデータが破損する可能性があります。したがって(ノートパソコン以外の)すべてのコンピュータに無停電電源装置は必要です。
(戻る)
(問い)デイスクアレイシステムを用意したほうがいいですか?
(答え)ハードデイスクにも寿命がありますので、大事なデータを保護するためにもRAIDシステムを導入することができればそれにこしたことはありません。
RAIDシステムはデータの安全性を求める場合・データ
に迅速にアクセスする場合(データベースのデータや画像データベースのデータなど)などに有用です。
プロフェッショナルドクターは通常のNASなどを用意してそこにデータをおいて運用することができます。
MySQLはRaidびHDDを装備したサーバー機が必要です。
(戻る)
(問い)K6を使用したパソコンでもだいじょうぶですか?
(答え)もちろんWindowsが稼動するコンピュータであれば大丈夫です。自作のコンピュータで運用しておられるユーザーの先生もたくさんおられます。ちょっと古くなったCPUや互換CPUはかなり安価に手に入りますので高性能のコンピュータをある程度安く作れる状態ではあるようです。
(戻る)
(問い)領収書の印刷はできますか?
(答え)もちろんできます。領収書だけを印刷して患者に渡したり、領収書と処方箋を、あるいは処方箋だけを印刷して患者に渡すこともできます。
(戻る)
(問い)院外処方せんの書式は決まっていますが、あらかじめ書式を印刷した紙に印刷することになりますか?
(答え)院外処方せんは白紙に印刷しますが、書式付で印刷されます。
(戻る)
(問い)院内処方をしたり院外処方をしたりなどの切り替えるをすることができますか。
(答え)院内処方モードにしたり、院外処方モードにしたり自由に切り替えて処方することができます。もちろん会計・レセプト作成についても処方のモードにしたがって処理されます。
(戻る)
(問い)薬剤種類数を減らしたりすることはできますか?
(答え)院内処方でも院外処方でも患者の薬剤自己負担金を減らすためには、現在の処方での薬剤種類数が205円ルールを適用した上での何種類に当たるのかを判定しなければなりません。プロフェッショナルドクターではカルテからボタンをクリックするだけで現在の処方内容での薬剤種類数を表示します。同時に投与法を修正するための参考として1日量ごとの薬価を表示しますので患者の自己負担を減らすために適切な投与法を検討することができます。
(戻る)
(問い)どのくらいの量のデータを保存することができますか?
(答え)プロフェッショナルドクターの一つのデータベースファイルの最大データサイズは1Gbです。プロフェッショナルドクターではデータベースファイルを5個から7個使用しています。そのうちデータが蓄積するファイルは2個です。ただし、アタッチするテーブル(ハードデイスクも)を分散させればもっと増やすことができます。しかし、データベースでは、データは検索その他の機能との関係で適切な量が決められます。たとえば、一人の患者が1回受診すると、平均して約1000バイトのデータが増えることがわかっています。1Gbのハードデイスクには100万回分のカルテ(1日100人の外来患者数なら、27年分)が単純計算で収容できることになりますが、それだけのデータを収容したカルテシステムでは速度が遅くなり、実用性はなくなります。したがって、最近2、3年分のデータのみを収容しておいて、それ以前のデータは別に保存するという方法が妥当でしょう。
なお、最近ノーバメデイコではデータが蓄積した状況下でも日々のカルテ入力や会計業務などの業務上のデータ処理に要する時間が遅くならないようにプロフェッショナルドクターを改良するバージョンアップ作業を開始しています。これはキャッシュ更新を用いたもので、10年分くらいのデータが蓄積しても日常の処理はデータが数百件のときと同様の処理時間で行えるという画期的なものです。
MySQLを使用するMyProdocはデータ量の制限はありません。サーバーの記憶装置の容量に依存します。
(戻る)
(問い)プロフェッショナルドクターを、会計とレセプト作成に使って、カルテは従来通り手書きにしたいが、その様な使い方はできるだろうか?
(答え)もちろんできます。ただ、その様な使い方をするのであれば、レセコンを使用されても同じことだと思いますがどうでしょう?
値段が安いから?!
確かにプロフェッショナルドクターがレセコンよりもコストパフォーマンスが優れています。ただ、プロフェッショナルドクターは手書きのカルテをなくすことで診療に関するデータを一元化するために生まれたソフトですから、その様な使用法はもったいないような気がします。データを一元化することで思いもかけないようなことが可能になるのです。
(戻る)
(問い)レセプトに必要なコメントの入力はできますか?
(答え)コメントの入力は可能です。
(戻る)
(問い)今までコンピューターに触ったこともないのですが、本当に手書きの3分の1の時間でカルテが書けますか?
(答え)手書きのカルテが時間がかかるのは、同じことを何度も繰り返して書いたりする必要があるからです。たとえば、10種類も薬を投与している患者さんの処方せんは手書きであればやはり全部かかなければならないでしょうから時間はかかります(今まで全部看護婦にやらせていたという方は別ですが)。プロフェッショナルドクターはレセコンの処方箋発行のようにDo処方で自動的に発行ができますし、薬の入力もプルダウンメニューからの選択ですから、はるかに早く入力することができます。それにキボード入力は慣れると手書きよりも早く入力することができますし、疲れません。定型文の入力をフル活用すればもっと早く書けるかもしれません。
コンピューターに触ったこともないという方はプロフェッショナルドクターを使用する前の準備段階から苦労されることが予想されます。前もって遊び半分ででもパソコンに慣れておかれることは必要だと思います。実際上プロフェッショナルドクターを使用するようになって初めてパソコンを使うようになったという方はおられますが、例外的です。一方、導入してはみたが使いこなすまでにはいたらずそのままになっている、という例もあります。
プロフェッショナルドクターは一番簡単なデータベースを使用しているとはいっても、ネットワーク上で運用するデータベースシステムであり、データベースシステムにはネットワークの保守・データの保守などデータベース特有の問題が発生します。ワープロソフトを起動して文書を作成し、作成したら保存して終了する、というように単純に処理できるものではありません。
また基本的にこの製品のコンセプトは、できるだけ医療事務にかける経済的負担を省きたいという方のためのもので、自分で処理する必要のある事も多く、コンピュータ全般に対するスキルがある程度必要です。
したがってまったくのパソコン初心者やマックしか使ったことがないという場合には無理があるといわざるを得ません。実際上導入後に使い切れないという不満が出てくるのはこのような方からです。
したがって、パソコンのスキルが一定以上でない場合はお勧めしません。
この場合一定以上のスキルがあるかどうかを判断する方法として使用する尺度はコマンドラインの入力ができるかどうかということです。
MyProdocはパソコン初心者には最初から導入運用は無理です。
パソコンのパワーユーザーであることはもちろんの上、ある程度データベースを理解している方でないと使いこなすことはできないでしょう。
(戻る)
(問い)健康診断書や検査伝票などはどうなっていますか?
(答え)健康診断書は縦書き、横書きのどちらの書式でも印刷されます。医師は病名と診断内容のみを入力すればあとはシステムが自動的に入力してくれます。また、検査伝票は検査指示を出しておけばそのまま伝票として印刷されます。
(戻る)
(問い)検診や予防接種や自費の患者の場合はどのようにしますか?
(答え)通常どおりの処理をしますが、レセプトシステムにはデータが渡されないようになっていますので気にせずにカルテを記載できます。
(戻る)
(問い)外来の包括制への対応はどうなっていますか?
(答え)包括制を取る場合は会計も自動的に包括の内容に応じた処理をしますし、レセプトも対応した印刷をします。
(戻る)
(問い)検査センターからの検査データを電話回線でプロフェッショナルドクターに自動的に取り込めますか?
(答え)検査センターもいろいろな会社があり、各社がそれぞれの方法で検査データを送っていますのでなかなか難しい問題です。しかし、検査センターがプロフェッショナルドクターの検査データと同じ形式(データの並び)で検査データをテキストファイルにしてくれれば可能です。テキスト形式からテーブルに取り込むことは簡単にできますので、テキストファイルを電子メールなどで送ってもらえば簡単に取り込めます。
98年10月1日出荷分からのプロフェッショナルドクターではテキストファイル化した検査データの自動入力機能がついています。
この機能を使用すれば検査センターが医療機関の検査データをテキストファイル(CSVファイル)にさえすればそのテキストファイルをフロッピーデイスクや電子メールなどで受け渡しするだけで検査データの自動入力が可能です。
(戻る)
(問い)院内業務を電子カルテシステムで処理する場合に、処置室やX線室など各部門への連絡はどのようにしてすることができますか?従来はカルテを持ち運んでいたので、連絡が問題になることはなかったのですが。
(答え)受付と診察室には必ずコンピュータがあるでしょうから受付画面あるいは診察画面の処置欄に連絡事項を記載できます。受付画面あるいは診察画面の処置欄に記載した項目は他のコンピュータにも表示されますから、処置室、あるいは薬局にコンピュータがあれば、処置の指示が出ていれば、カルテを開いて内容を確認した上で処置をし、あるいは診察の終了したカルテの処方箋を見てあらかじめ調剤しておくということが出来ます。しかし、処置や調剤もやはり紙に打ち出したものを見て処置・調剤を行うのが心理的にも安心できるようです。ですから、処置室や薬局にコンピュータがあるから何でもCRT上で見て行うことが出来るということにはなりません。伝票や処方箋をプリントアウトしてそれをみて処理することが確実です。診察が終了したことを確認した時点で、各部門に必要な伝票なり処方箋なりを印刷し、それを見ながら必要な処理をするということになるでしょう。
なおWindows NTではコンピュータ同士でベルを鳴らして電話をかけあう事が出来ます。これはパソコン通信でおなじみのチャットと同じようなものです。院内の連絡に便利ですのでご利用になるとよいと思います。
(戻る)
(問い)レセプトを印刷しながら診察など日常業務は出来ますか?
(答え)プロフェッショナルドクターは日常診療にはカルテシステムを起動して使用し、月初めのレセプト作成業務にはレセプト作成システムを使用します。
一つのコンピュータ上でレセプトシステムとカルテシステムを同時に開くことは出来ませんが、一つのコンピュータでレセプトシステムを開いてレセプトを印刷しながら、他のコンピュータではカルテに入力したりなど通常の業務を並行して行うことは出来ます。ですから日常業務をしながら勤務時間内にレセプト発行を終了することが出来ます。ただそれをするにはコンピュータが三台(1施設内で)あった方がやりやすいと思います。
MyProdocの場合は、端末が何台あっても高速処理が可能です。
(戻る)
(問い)レセプトを印刷している途中に領収書・処方箋などを印刷する必要が出てきたときはどうしたらいいですか?
(答え)自院にプリンタが1台しかない場合、診療中に処方箋などを印刷する必要が出る可能性があるときには、たとえば1000枚のレセプトの印刷を開始することなどは控えたほうが良いでしょう。このように最初にオーダーした1000枚の印刷よりも後でオーダーした1枚の書類が急ぐような場合はワープロ文書の印刷などでも当然おこり、印刷物の優先順位の問題ですからプロフェッショナルドクターにのみ発生する問題ではありません。レセプトの印刷を開始したのち処方箋を印刷した場合にはプリンタ内にドキュメントが送られてすべてが印刷されていない場合にはWindows上でプリンタを表示し、ドキュメント(=レセプト)を削除することはできますが、すでに印刷を開始してプリンタ内にドキュメントが残っていなければプリンタの電源を切るか、印刷が終了するのを待つしかありません。したがって診療時間内にレセプトを印刷したい場合はプリンタが2台あったほうが良いでしょう。実際プロフェッショナルドクターを導入している施設では複数のプリンタを使用されていることが多いようです。
(戻る)
(問い)レセプト500枚を印刷するのにどのくらいの時間がかかりますか?
(答え)カルテで作られたデータを変換するのに約2~3分、印刷するのに1分間にレセプト20
枚可能です。これはEpson LP9200Sというレーザープリンタでの結果です。以前((95年版)はレセプトデータの変換にもっと時間がかかっていましたが、現在では従来の10分の1の時間で出来るようになりました。これは島根県のある古いユーザーの先生のアドバイスにより改良したものです。印刷時間はプリンタの能力にもよります。1分間に20枚の速度ですと500枚のレセプトも25分で印刷が完了します。
(戻る)
(問い)月の途中でレセプトを印刷する事ができますか?
(答え)レセプトは月単位で提出しますので、月の途中でレセプトを印刷すると患者がその月に再度受診した場合に印刷し直す必要が出てきます。ですからなぜそのようなことをする必要があるのか疑問ですが、レセプトはどのように期間を区切っても作成することが出来ますので、もちろん可能です。
(戻る)
(問い)返戻のあったレセプトを修正し印刷することはできますか?
(答え)レセプトは電子カルテのデータをもとに作成しますので、電子カルテのデータがある限り、いつのレセプトであっても再現することができます。
(戻る)
(問い)レセプト作成時にレセプトの実物と同じイメ-ジで表示,訂正,修正できますか?
(答え)
打ち出したレセプトはデータベースのレポートという印刷オブジェクトであり、データ入力のためのフォームとも異なり、また保存されるデータそのものとも異なるものです。データベースのデータは複数のテーブルに分散して保存され、見ただけでは何を示しているのかは全くわかりません。そのようなデータを組み合わせてレセプトという一つの書式を持った印刷物を作成するわけです。ご存知のとおりレセプトに表示される事項は診療内容をすべて詳細に表示しているものではありません。カルテに記載されていてもレセプトでは省略されている項目もあります。
簡単にいえば詳細な電子カルテのデータを加工して、データの表示を省略したり、あるデータは表示したり、あるデータは集計値を表示したりした結果、診療データを比較的ラフに表示したレセプトができるということです。
また、プロフェッショナルドクターは単なるレセプト作成システムでなく、電子カルテであるということからもデータがレセプトのような単純な形式で保存されているわけではないということがご理解いただけると思います。
レセプトの実物と同じイメ-ジで表示,訂正,修正できればわかりやすく便利ですが、電子カルテの場合、レセプトを修正するということは電子カルテのデータを修正することですから、電子カルテのデータそのものを修正しその結果がレセプトに反映される、、、、という手順が必要になります。
従いましてプロフェッショナルドクターでは訂正画面などでレセプトデータを見ることはできますし、レセプトのプレビューの段階でレセプトの印刷イメージをみることはできますが、
レセプトの実物と同じイメ-ジで入力・訂正・修正しませんしその必要もないと考えています。
プロフェッショナルドクターでは電子カルテのデータを修正する結果としてレセプトのデータも変わります。
なお、MyProdocの場合、レセプトのイメージで点検が可能ですが、データの修正は元のカルテ画面を開いて、元データを編集します。
(戻る)
(問い)レセコンのデータを何とか生かして電子カルテに移行したいが、出来るでしょうか?
(答え)レセコンのデータをデータベースシステムのテーブルに取り込むには二つの処理が必要です。まず、レセコンのデータをMS-DOSのファイル形式にします。その後、データに区切りがなければ区切り記号をいれます。以上が出来ればそのままテーブルに取り込むことが出来ます。レセコンのデータをMS-DOSのファイル形式にするソフトはあるようです。データをコンバートする専門の会社もありますので、お問い合わせがあればご紹介いたします。
(戻る)
(問い)レセコンの患者データをプロフェッショナルドクターに入力するのに協力してくれますか?
(答え)プロフェッショナルドクターの導入は新規開業時よりも、開業中レセコン使用から電子カルテに切り替える場合が面倒です。いろいろな準備が必要になるからです。もっとも問題なのは患者データですが、最近はレセコンデータをCSVファイルに変換することはほとんどのレセコン会社が行っているようです。もし患者データ(頭書き情報)がCSVファイルになっていれば短時間にプロフェッショナルドクターの患者登録名簿に取り込むことができますので当社でいたします。
(戻る)
(問い)患者の登録数の制限やデータ保存の期間の制限はありますか?
(答え)患者の登録数の制限(たとえば1万人までなど)や期間の制限などデータの制限はありません。
あらゆるデータ数の制限はデータベースの限界(およびハードデイスクの容量)にだけ依存します。
(戻る)
(問い)印刷できるレセプト枚数の制限はありますか?
(答え)印刷できるレセプト枚数の制限はなく、何枚でも印刷可能です。
(戻る)
(問い)データが膨大になったときの対処法は?
(答え)データベースのデータは増えることはあっても減ることはありません。したがって、使用するうちにだんだんと動きが遅くなるのは確実です。レセコンと違って、電子カルテの場合はレセプト作成が終了したらデータを切り捨てるというわけには行きません。データがたくさん入っている方がデータベースとしては価値があります。反面、日常の診療・会計処理の速度からいえば出来るだけデータが少ない方がありがたいという矛盾した面があります。その折り合いをどうつけるかが問題です。データの増大にはハードの能力の拡大(CPU能力、メモリー増設)である程度対抗することが出来ます。1,2年後に出現するパソコンは現在の何倍もの能力を持っていることでしょう。ただ、現実には古いデータでほとんど参照することもないようなものをいつまでも引きずっていてもしようがないということもありますので、そのような場合の処理方法を検討する必要はあります。
現在考えられる、データ量の増加をそのままに事務処理の迅速化の要求を満足する方法を記載します。
データは増大したから切り捨てるということではデータベースとしての意味がありませんので、データは削除しない方が良いでしょう。データ.MDBを複製し、すべてのデータを保存するデータ.MDBと、日常の診療に使用するものに分けて使い分けます。これを仮に保存用データと日常診療用データと呼ぶとしますと、これらを別々のデイレクトリに名前をつけて保存します。日常の診療時には日常診療用データにアタッチして処理します。日常診療用データは保存用データのうち、ある年月日以後のデータに限ります。対象になるテーブルは診療録・診療・処方・検査画像診断・注射薬剤材料の各テーブルです。これらのデータの一部を削除する前に患者の過去のデータをすぐに参照できるようにしておく必要がありますが、その方法は以下の通りです。患者の診療のデータで大事なものはカルテのS・Oの各項目の内容、処方内容、検査項目などでしょう。これらはその患者のカルテを開くと、診療経過一覧、処方経過一覧のボタンで一覧を開くことが出来ます。開いたらコピーし、その患者の医学情報フォームを開いてその中の、診療経過サマリーの欄や、その他欄などに貼り付けておきます。診療経過・検査項目一覧を診療経過サマリー欄に、処方経過をその他欄にコピーしておくのがわかりやすいかも知れません。そうすることでカルテから患者医学情報を開くことにより、過去の記録をすぐに参照することが出来ます。データを二つに分けた段階で以後のデータは日常診療用のデータだけに保存されるようになりますので、時々、ある年月日以後の増加分のデータをまとめて保存用データに追加していく必要があります。これはアクセスからテーブル追加クエリーにより保存用データに追加していくことが出来ます。これらの方法に関してはおいおいマニュアルに記載してゆく予定です。必要がある場合は保存用データをアタッチ先にしてカルテシステムを開けばすべてのデータを開くことが出来ます。
ノーバメデイコではデータが蓄積した後でも日々のカルテ入力や会計業務などの業務上のデータ処理に要する時間が遅くならないようにプロフェッショナルドクターの設計変更を行いました
これにより、10年分くらいのデータが蓄積しても日常の処理はデータが数百件のときと同様の処理時間で行えるようになっています。
なお、MyProdocでは20年・30年以上に渡ってデータの蓄積が可能です。
(戻る)
(問い)プルダウンメニューからカルテの記載が出来るとのことですが、入力作業全体のうちどの程度までプルダウンメニューでできますか。
(答え)プルダウンメニューに記載できる事項はいくつでも増やすことが出来ますので、やろうと思えば大部分の入力をプルダウンメニューから選んでクリックするだけでカルテを記載することが出来ます。ただ、カルテの記載事項の中で、A・Pの各欄はプルダウンメニューからの入力は出来ません。アセスメントやプランは類型化しておくことは不適と考えたからです。
項目は不足なものは御自分で必要と思われる項目を入力しておく必要があります。あらかじめ入力しておく方法は簡単です。入力した言葉の区切りとして必ずセミコロン;を入れておいてください。
また、97年版から無制限の約束処方・約束検査・約束注射・約束診療の登録が可能になり、プルダウンメニューからの項目の選択で一度に多項目を入力することができます。したがって、ほとんどの入力をマウス操作のみで行うことも実際に可能になりました。
(戻る)
(問い)カルテに絵を描く場合に必要なソフトはありますか。
(答え)カルテに絵を描くには、カルテの図の欄をクリックして、メニューから編集→オブジェクトの作成と貼り付けを選択します。するとコンピュータにインストールされているWindowsアプリケーションがすべて表示されますので、そのうちからドローイングツールを選択するとそのソフトが起動されます。後はそのまま絵を描いたり、人体の各部の図があらかじめ入っていればそれを呼び出して加工します。 Windowsにはペイントブラシがありますので通常はペイントブラシで絵を描くことが出来ます。
(戻る)
(問い)しばらく来院していない患者や特定の病名の患者を抽出してダイレクトメールの宛名印刷をするなどということはできますか?
(答え)可能です。
(戻る)
(問い)レセコンのデータや電子カルテのデータはソフトを決めてしまうと後で別のソフトなどに移すことはできないのでしょうか?レセコン会社はデータを移せないといっていますが。
(答え)一般にデータベースのテーブルのデータは互換性があるものがほとんどです。互換性という意味はAというデータベースからBというデータベースへ直接にデータを移せなくとも一度テキストファイルにすれば別のデータベースのテーブルに取り込めるということです。ですからアプリケーションを換えてもデータを生かすことはできます。ただし、レセコンの場合は本当に互換性のない場合もあるかもしれません。互換性があったとしても他のシステムに乗り換えられるのを避けるためにデータを移せないというのはレセコン会社の使う常套手段です。いずれにせよ将来の発展性のないレセコンとは早めに縁を切るのが良いでしょう。パソコンの世界ではオープンなデータベースを模索していますからデータが生かせなくなることはありません。レセコン会社は大手の会社でないとメンテナンスがうまくできないといいますが、むしろ今後はレセコン会社の方が難しくなってきます。なぜならば、パソコンベースの医事ソフトが増えてきたためにレセコン会社は従来のように大きな利益を得にくくなりました。今後先細りする一方ですが、今後電子カルテを使用するようになっていくと、ますますパソコンベースのシステムへの移行が必要になり、ますますレセコンメーカーは価格的に対抗できなくなります。そしてある日突然撤退を余儀なくされるのです。パソコンベースのソフトの場合は他のソフトに乗り換えようとすれば簡単に従来のデータを生かした形で乗り換えることができます。ブラックボックスであることで価格を維持してきたシステムの業界が危機に陥っているのが現在の状況です。
(戻る)
(問い)開発者は医師だそうですが、参考のために開発者のシステム環境を教えてくれませんか
(答え)
以下は1998年頃のデータです。現在はServer仕様機3台(Raid HDD)、端末はWindows2000、XPが主流です。CPUはGHz単位、メモリーは256から500Mbからバイトとなっています。
(1)NEC(CPU:Pentium Ⅱ・266MHz、メモリー96Mb)Windows NT 4.0 Server
(2)IBM(CPU :Pentium 200MHz、メモリー64Mb)Windows 95
(3)IBM(CPU :Pentium 166MHz、メモリー48Mb)Windows 95
(4)NEC(CPU:Pentium 90MHz、メモリー32Mb)Windows NT 4.0 Workstation
(5)NEC(CPU:Pentium 90MHz、メモリー48Mb)Windows NT 4.0 Workstation
(6)IBM(CPU :Pentium 266MHz、メモリー96Mb)Windows 95
(7)その他(CPU:Pentium Ⅱ・400MHz、メモリー128Mb)Windows NT 4.0 Workstation
(8)SONY Vaio(CPU :Pentium 233MHz、メモリー96Mb) Windows 95
(9)その他(CPU:Pentium Ⅱ・450MHz、メモリー256Mb)Windows NT 4.0 Workstation,Windows 98
(戻る)
(問い)厚生省が電子カルテを作る計画だそうだが、対応できますか。
(答え)電子カルテの必要条件はLAN対応、マルチメデイア対応であることの二つです。これをクリアすれば誰にでも同じようなものが出来ます。厚生省にとって一番の問題は開発環境やOSを何にするかです(Javaで開発すれば別ですが) 数年後にはWindowsに変わる新しいOSが支配的になっているかもしれません(いずれはUNIX全盛の時代が到来するのではないかと思いますが、もはやOS自体が不必要という時代になるかもしれません) 開発するのに何年もかければパソコン環境がすっかり変わってしまいます。このように進化の速度の激しいもののなかでシステムの統一化などということは不可能であり無意味です。UNIX,Windows、Macなど汎用OS上で動く電子カルテを作ったら、マスターコードなどの統一がなされ、電算化に向かない処理を強要することもないでしょうから、厚生省が研究すること自体は歓迎しますが、厚生省が電子カルテを完成する前に、民間で開発されたいろいろな電子カルテが普及してしまっているでしょう。汎用OS上で動くものでないような電子カルテであればそっぽを向かれるでしょう。しかし結局のところ、官主導のものは実用にならないというのがこれまでの経験則からの結論です。
おそらく可能なのはマスターの統一化くらいでしょう。マスターに関しても問題があります。それは電子カルテマスターとレセプト電算システム用のマスターが別々のものだということです。これはマスターを作成する厚生省関連の財団法人が別々であるからです。
最近厚生省では電子カルテのマスターのうち病名マスターを完成しており、他の診療行為などのマスターの作成準備もしています。完成したマスターは公開・配布されますのでその際にマスターを導入してコードの共通化を確保することもできるでしょう。しかしすでに完成した病名マスターを見ますと、従来の傷病名マスターよりも項目数が多くなっていますが、右・左などの修飾語がありませんのでこのままではレセプト出力用のマスターとしては使用できません。
おそらく病名マスターに限らず電子カルテマスターでは、電子カルテの入力には便利だがレセプト上のデータを出力するには不適当というようなコード体系が作成されることになる可能性があります。これはレセプト電算システムに使用する厚生省マスターと電子カルテマスターが併存する当然の帰結で、厚生省内部でも縦割り行政が行われていることを示唆しています。
電子カルテのデータを入力してもそれがそのままレセプト用のデータとして使用できないとなりますと、厚生省マスターがデータ入力用のマスターになり、電子カルテマスターは単に情報のやりとりをするためにだけ使用されることになる可能性があります。
(戻る)
(問い)電子カルテには興味があるが、電子カルテは法律的に認められていますか
(答え)開業前に都道府県の保険医療福祉部などに電子カルテを使用したいと打診された先生からのお問い合わせですが、カルテをコンピュータで入力することは以前から禁止されてはいません。ワープロによる手紙が禁止されていないのと同様です(誰に禁止する権限があるでしょう?)
電子カルテの使用についていずれかの行政機関に”了解”を得る必要はまったくありません。またどのような電子カルテが認められてどのようなものが認められていないということもありません。
以前は電子カルテは認められていなかったという認識が強かったのですが、以前も電子カルテはカルテとして無効ということではありませんでした。単に、磁気記憶媒体のままで電子カルテの記録を残すのは不十分で、カルテを紙に印刷して残す必要があったということです。
現在でも手書きのカルテでないとだめだと思っている人もいますが、そんなことはありませんのでご安心ください。これらについては2年前の医事新報(日本医事新報No.3751、142頁、「電子カルテの使用と留意点」)に厚生省の役人(厚生省健康政策局総務課医療技術情報推進室長)が厚生省の見解として答えています。コンピュータ入力で印刷しようと手書きであろうと、要は印刷されたカルテの記載事項が法律の要求する必要事項を満たしていれば問題ありません。
これは厚生省や厚生省の役人の見解がどうであろうと関係なく当然のことです。
プロフェッショナルドクターはこの点について周到な配慮をしています。
99年5月に厚生省は電子カルテのデータの保存に関して従来の方針を改め、紙による保存以外に磁気媒体のみによる保存もカルテとしてみとめるという通達を出しました。
基準として、データの
①真正性の確保
②見読性の確保
③保存性の確保
が求められます。これを満たすには電子カルテにもよると思いますが、プロフェッショナルドクターの場合はデータが含まれたデータベースファイルをCD-Rに書き込んで保存することで条件は満たされます。
(戻る)
(問い)厚生省が電子カルテを認めたということを聞きましたがプロフェッショナルドクターは厚生省の電子カルテの要件に適合しますか?
(答え)厚生省が電子カルテを認めたということは一定の条件下で磁気媒体での保存を認めたということです。従来電子カルテのデータの保存とは別にカルテを紙に印刷して保存していましたが、データを保存しておけば紙に印刷する必要はないということになります。しかし、データを改ざん不能な態様で保存し、真正性の確保が求められます。プロフェッショナルドクターの場合どのようにしたら適合するデータ保存が可能でしょうか。ハードデイスクやMOなどでの保存は書き換え可能ですから不適でしょう。現在考えられる適合する媒体はCD-Rです。CD-Rに保存したデータに電子カルテを接続してそのままカルテなどを打ち出したり、読むことができますし、追記はできても書き換えは不能ですから、プロフェッショナルドクターではデータファイルをCD-Rに書き込んで保存することで厚生省のデータ保存の条件に適合します。
なお、お問い合わせの趣旨が<プロフェッショナルドクターが厚生省が認める電子カルテのシステムとしての要件に合致するか>ということであれば、厚生省は、どのような電子カルテを認め、どのような電子カルテは認めない、ということを決めているわけではありません。今後もこのようなことを決めるということはないようです。
(戻る)
(問い)紙のカルテを保存しないでCD-Rに保存するとしてデータ保存の規格にマッチしたCD-Rはありますか。
(答え)
紙のカルテを不要とするための電子カルテデータ保存の基準として、データの
①真正性の確保
②見読性の確保
③保存性の確保
が求められるだけで、厚生省は具体的にCD-Rがよくて他の媒体はだめだとかを通達したわけではありません。①~③の条件を満たす磁気媒体が現在のところCD-Rであるということです。なお、この場合の保存とは自院で保存する場合の話で、もし法務局などに供託する場合であればどのような(書き換え可能でも)媒体であっても問題はないでしょう。ただ供託などは実際問題として現実的ではないのでCD-Rによる保存ということになるわけです。
(戻る)
(問い)現在レセコンを使用して特に問題もないし、電子カルテを導入すると従業員が抵抗するのではないかと思うのですが、どうしたらよいでしょうか。
(答え)公立の医療機関や従業員がレセコンに慣れていてしかもコンピュータに疎い場合などには電子カルテの導入に抵抗を受けることがあります。
現在レセコンを使用していて不満も問題もなく、手書きのカルテにも満足しているという現在の状態であれば何も急いで電子カルテを導入する必要はないと思います。無理に導入すればいたずらに混乱を引き起こす結果になるだけかもしれません。ファッション的に電子カルテを導入してもあまりいい結果は生まれないと思います。院内の無駄な労力を省くとか、医師としても診療時に電子カルテに入力することでカルテ記載を簡単にして浮いた時間を検査などの時間にまわしたい、などという目的のために生まれたソフトです。実際は導入されたプロフェッショナルドクターを使用して一番喜んでいるのは事務職員のようです。電子カルテを使用すると院内の作業が合理化されて事務の負担が減るためです。医師が電子カルテに入力することは従来の紙のカルテに書き込むこととレセコンにデータを再入力することを同時に済ませていることになります。
院内でドクターだけが電子カルテシステムを使用して入力するということだけでもドクターにとってずいぶんカルテ記載の手間が省けるかもしれません。Do処方などがボタン一つでできるからです。紙のカルテに書き込まないですむというのはドクターにとって大きな省力化になります。
(戻る)
(問い)診療に使用中にハングアップしたらどうなりますか?レセコンは動作異常時に駆けつけてくれるが、このようなソフトではそんなサービスは受けられないのが心配です。
(答え)
ハングアップしたときは再度ソフトを立ち上げます。
プロフェッショナルドクターは発売後2年半になりますが、原因不明のハングアップで業務が停滞したということはありません(原因不明のネットワークエラーが出たということはありますが、これはハードの問題です) ハングアップしたとしても回復の方法も確立しています。ハングアップしたからデータが破壊されるということもありません。
もともとレセコンと違ってブラックボックスではありませんのでハングアップしたとしても別に慌てる必要はないわけです。レセコンはトラブルが起きたときに専門の保守要員を呼ばないとどうしようもないというシステム自体に問題があるわけですから、レセコンがサービスが行き届いていたということではないのです。
日常、パソコンでワープロソフトを使用していてハングアップしたから業者を呼ぶ必要があるかというとそんなことはありません。それと同じことです。この辺の感覚がよくお分かりにならないとしたら、パソコンの初心者であると思われますので、現段階ではレセコンをお使いになったほうがベターかもしれません。
ただし、電源を突然切ったり、ネットワーク接続を切断したりなど、データそのものが破壊される恐れのある行為をしないように、ネットワークの管理などには細心の注意を払う必要はどのような場合も存在します。
現段階では院内LANによる電子カルテシステムを使用するのはまったく新しいことをやろうとするわけですから、ある意味で一つの冒険です。このような冒険はある程度パソコンを使いなれている方に向いているでしょうが、まったくのパソコン初心者には荷が重いかもしれません。しかしLANによる業務のコンピュータ化は医療界以外のビジネス社会では一般的なことであり、このようなシステムを導入することが冒険であるといわざるを得ないのは医療界でのコンピュータ利用が遅れているからではないでしょうか。
将来の大きな流れをつくるのもとしてパソコン院内LANによる電子カルテシステムが現実に広がりを見せているのは紛れもなく事実です。
2004年の段階では、小さなクリニックでの電子カルテもSQLベースのデータベースを導入することが常識となりつつあります。
MyProdocはMySQLを使用してきわめて低コストでSQL電子カルテシステムを構築できる環境をいち早く作り上げました。
(戻る)
(問い)開業を予定しているので医院の設計図を完成しなければならない。電子カルテを使うとなると職員の動線も従来の医院とは違うだろうと思うがその辺のアドバイスがほしい。
(答え)基本的に電子カルテを使用するからといって職員の動線がまったく変わってしまうことはありません。受付の職員がカルテを持ち運ぶという動きは確かに不必要になりますし、他の職員の動き自体も少なくなるかもしれません。しかし診察室と受付との連絡がまったく必要なくなるというわけではありませんので、従来のとおりの医院建築の考え方でいいのではないでしょうか。最近の傾向として、診察室はできるだけプライバシーが保てるように密室的な仕様に近づけたいというドクターの希望があるようです。プロフェッショナルドクターでは受付で患者を受付したと同時に診察室からマイクで患者を呼びいれるというようなことも可能ですから、電子カルテはそのような傾向にマッチしていると思われますが、診療はドクターだけでやっているわけではありませんし、緊急時のことを考えますとある程度の開放性は残すほうがいいかもしれません。しかしこれは個人的な意見であり、診療科によっても相当異なる考え方があると思われます。
電子カルテを使用する場合、LANケーブルで医院内のコンピュータを置く各部署を連絡する必要が出てきます。電話線と同じように壁の内部の配管内にケーブルを通すことが多いようですが、管の内部に通すときにケーブルに無理な力がかかることがあり、トラブルの原因になりますので、できれば床に配線する方をお勧めします。
また現在電子カルテを導入しないとしても、将来必ず必要になりますのでLANケーブルを設置できるように工事しておかれることをお勧めします。
(戻る)
(問い)開業後バーコードリーダーを使用して患者の受け付けをしたいが、プロフェッショナルドクターでできますか。
(答え)実はプロフェッショナルドクターを開発するときに、何とかバーコード・バーコードリーダーを利用したシステムを作りたいと考えていましたが、医療機関の業務を分析していくうちに、残念ながらバーコードの出番はほとんどないという結論に達しました。その結果、完成したプロフェッショナルドクターはバーコードを一切使用していません。
バーコード・バーコードリーダーは”多数の物を短時間のうちにシステムに入力する”必要があり、その”物が固有のバーコードを表示してる”という場合に有用です。
まさにスーパーのレジはバーコード・バーコードリーダーが働く格好の場所です。翻って小規模医療機関の業務を見たときに、一日の患者が1万人で窓口に5人も受け付け係りがいるというような施設であればバーコドリーダーがなければ業務が停滞すると思いますが、多くて300人程度の患者を受け付けするのにバーコードが必須であるとは思われません。プロフェッショナルドクターはユーザーの先生からのアドバイスをもとに機能の拡張をしてきましたが、やはり現在まで開業の先生からバーコードを利用する必要性のご指摘はまったくありませんでした。
現在のデータベースシステムはコンボボックスを使用して物の名前そのものを入力できるので、患者の受け付けにしろ薬剤の処方にしろすべて名前の一部を入力することで処理できます。バーコードを印刷した診察券を忘れる患者はいますが自分の名前を忘れる人はいませんから、プロフェッショナルドクターは名前を入力の基本としています。必要なものは作りますが費用対効果という面からも不必要なものは作らないというのはプロフェッショナルドクターの基本的な考え方です。現在のところ今後の機能拡張の予定にもバーコード・バーコードリーダーの利用は含まれていません。
もちろんバーコードを使用することはできますのでご自分でカスタマイズしてください。
(戻る)
(問い)将来レセプトを紙でなくフロッピーデイスクで提出するようになるそうですが、対応できますか。
(答え)いわゆるレセプト電算処理システム(磁気レセプト)のことですが、現在兵庫県などで実験的に行われています。その内容を見ますと、現在の紙のレセプトの表示方法よりも理に適ったデータ表示法が採用されており、コンピュータ処理上からはレセプトのあるべき姿に近いと思われます。現在のレセプトは手書きとコンピュータ処理の両方で処理されることを想定しているためにコンピュータ処理にとってはかえって面倒な部分があります。
紙のカルテを提出するよりは便利ですし、磁気レセプトは原理的には電話でも提出できるわけですから、プロフェッショナルドクターは将来対応する計画で、現在レセプトシステムの変更作業を進めています。しかし厚生省が将来作成する電子カルテ用のマスターと、レセプト電算処理システムで使用するマスター(=厚生省マスター)とは別々のものですのでこれら2種類のマスターの関係が明らかになる必要があります。
MyProdocは2005年から磁気レセプトシステムに対応予定です。
(戻る)
(問い)開業準備でいろいろと金がかかる。プロフェッショナルドクターを購入するのに一括支払い以外の方法はないだろうか。
(答え)プロフェッショナルドクターはリースで購入可能です。3年リースの場合支払いは毎月25000円程度になります。
MyProdocは導入時25万円のみで可能です。
(戻る)
(問い)レセプトチェック機能はありますか。
(答え)プロフェッショナルドクターでのレセプトに表示する病名のチェックするための機能は以下のとおりです。
①レセプトに病名がない患者のレセプトはエラーが表示され印刷することができません。
②院外処方の場合に処方した薬剤と病名をチェックすることができます。
③特定の検査・処置などを行った患者の病名をチェックできます。あるいは初診などの患者の病名をチェックすることが可能です。
ノーバメデイコでは審査委員としての目で自動的にレセプトを審査する機能が作れないだろうかということを考えてその開発に着手しましたが、なかなか難しい問題です。というのも検査・診療行為などに対して必要な病名があらかじめ決められているわけではありません。どのような病気に対してどのような医療行為を行うかについては医師の裁量の範囲が大きいからです。診療に関する医師の権限を考えるとこれは当然のことで、診療行為が医師の裁量に任せられる以上、ある病名に対する医療行為も医師の裁量によることになります。決して機械的に処理できるものではありません。つまり最終的には診療する医師と審査委員との考え方の差が問題になるわけです。レセプトチェック機能というのはそのレベルまでいくことは到底不可能で、せいぜ不注意による記載漏れなどをチェックする程度にならざるを得ないからです。しかし今後の課題として開発を進めていきます。
(戻る)
(問い)レセプトの印刷方法はどうなっていますか。書式を印刷した紙に印刷するのかそれとも白紙の紙に書式付で印刷するのですか。もし後者の場合、プリンタのトナー代などのランニングコストが馬鹿にならないのではありませんか。
(答え)プロフェッショナルドクターではレセプトは白紙に書式付で印刷するのですが、レセプトの印刷がA4版になる以前は、あらかじめ書式を赤や青などのインクで印刷した色とりどりのレセプト用紙(印刷会社に発注したもの)
にレセプトデータだけを印刷していました。印刷時に罫線とのずれを修正する機能が必要だったり面倒な面がたくさんありました。各医療機関でレセプト用紙を発注する場合、一度にたくさん印刷しますと、1枚あたりの印刷コストは下がりますが、途中で制度が変更になってせっかく印刷した用紙が大量に無駄になることもありましたし発注量をどの程度にするかが問題でした。
規制緩和の一環でしょうか、現在のようにA4版のレセプトで黒インクで白紙の紙に書式が印刷できるようになったことは大変喜ばしいことです。罫線を印刷する場合、レーザープリンタのトナー代がかかるのではないかとのご心配ですが、レセプト1枚あたりトナーのコストは3円~4円程度(これは新品のトナーを使用した場合で、リサイクルトナーを使用すれば2円以下です)紙代は50銭~1円程度です。したがってあらかじめ印刷したレセプト用紙を使用する場合と比較してランニングコストは変わりません。制度が変わってせっかく印刷した用紙が無駄になってしまうこともありませんから、現在のように白紙に書式を印刷するほうがトータルではずっと安くなるはずです。
(戻る)
(問い)レセコンのリース期間がまだ残っているので電子カルテとレセコンをつないで使用したいが、できるでしょうか?
(答え)不可能なことではないとは思いますが、プロフェッショナルドクターは電子カルテで入力したデータをもとに通常のWindows対応のプリンタから直接レセプトを高速に印刷できます。それをわざわざ既存のレセコンに接続してそのまたレセコンに接続されたレセコン専用のプリンタからレセプトを打ち出すというのは、大変な労力を要すること(物理的に接続すればすむ問題ではありませんので)を考えますといかにも無駄なことではないでしょうか。
(戻る)
(問い)カスタマイズをしないと使用できるようになりませんか?
(答え)プロフェッショナルドクターは通常カスタマイズは不必要です。診療などに必要な機能はほぼそろっているからです。機能が充実していますのでプロフェッショナルドクターをご利用の先生方もすべてての機能を利用されているわけではありません。開発者も日常デフォルトの機能しか使用していません。
(戻る)
(問い)カスタマイズの希望に応じてくれますか?
(答え)カスタマイズは御自分で行ってださい。
最近このようなご要望が増えてきていますが、プロフェッショナルドクターがカスタマイズ可能な形で供給しているのは
当社がユーザーのご希望に応じてカスタマイズするためではありません。ユーザーごとに改造したい点は異なるでしょうからユーザーがご自分で改造することができるようにするためです。
プロフェッショナルドクターは診療その他に必要な機能はほぼそろっています。
しかし御自分の施設で特定の機能がほしいということは当然あるわけですが、普遍的に必要なものとはいえず特殊な機能であれば御自分で追加していただくことになります。自分でできないカスタマイズはすべきではなく、自分のできる範囲内で行ってください。自分でできないものをユーザーでない第3者に依頼することはできません。
もしその機能が普遍的に必要なものであれば当社でその機能を追加します。
プロフェッショナルドクターはこのようにして機能を拡張してきました。またプロフェッショナルドクターの機能がそろっているとは言ってもまだまだ電子カルテとしての可能性があるはずです。あっと思うような機能が実現できるかもしれません。
プロフェッショナルドクターはユーザーの先生方のご希望に沿ってより良いものに近づけていくというソフトですから、アドバイスや改良を要する点のご指摘はご遠慮なくお寄せください。ただし自分でできないカスタマイズを当社に依頼することはできません。
(戻る)
(問い)デモ版を使ってみたが自分の希望の通りに改良してくれますか?
(答え)
試用版のユーザーのご意見を元に、試用版のユーザーのご希望に従って正規版の仕様を変更して出荷するということはいたしておりません。正規版を購入後にご自分で好きなように改造してください。
(戻る)
(問い)自分でカスタマイズしてデータの統計的な処理ができますか?
(答え)できます。プロフェッショナルドクターはテーブルのデータをもとに問い合わせをいろいろ作ってご自分でさまざまにデータを加工することもできます。新しい機能を追加することもできます。ドクターにより電子カルテを使ってやりたいことが異なりますので、各人でいろいろな機能を追加することができるのがプロフェッショナルドクターの特徴です。
(戻る)
(問い)自分でカスタマイズしようと考えているがシステムの構造などがわからないときに相談に乗ってもらえますか?
(答え)プロフェッショナルドクターは医師の相互扶助という目的のもとに開発されたソフトですから、プロフェッショナルドクターのユーザーの方からのご質問やご相談を歓迎しています。今後もできるだけのご協力をしてドクターが快適な環境で診療ができるように尽力してまいります。
(戻る)
(問い)プロフェッショナルドクターのデータに接続して他のソフトで使用することはできますか?
(答え)プロフェッショナルドクターに蓄積されたデータに接続して、たとえばDelphiなどでデータベースソフトを作り、別の目的に使用することも可能です。テーブルを使用したDLLファイルを作ることもできます。
またデータをdBASEテーブル、Excel、HTMLドキュメント、各種テキストファイルにして使用することもできます。
(戻る)
(問い)現在エクセルに患者のデータを入力していますが、プロフェッショナルドクターで利用できますか?
(答え)ACCESSテーブル、dBASEテーブル、Excel、HTMLドキュメント、各種テキストファイルをプロフェッショナルドクターで利用することが可能です。
(戻る)
(問い)実際にプロフェッショナルドクターを導入するときには具体的にどのようなものをそろえたらいいのかを知りたい
(答え)まず、パソコン、プリンタなどのハードが必要です。すでにお持ちの方はそのパソコンにあったLANボード(10BASEまたは100BASE T)が必要です。パソコンの販売店でまとめて購入されると良いと思いますが、院内LANに必要なものは次の通りです
(1)LANボードをセットしたパソコン
(2)HUB1個、及び複数のパソコンをつなぐケーブル(LANボードの規格にマッチしたもの)
(3)プリンタ(1台か2台)
(4)無停電電源装置(必須・コンピュータの台数分)
(5)必ずしも必須ではありませんが、バックアップまたはデータ保存用のMOドライブあるいはテープデバイスのようなリムーバブルな記憶装置(1台)
(6)CD-R 1台(99年5月から紙のカルテの印刷は磁気媒体で保存可能になりましたので、カルテを印刷しない場合)
(戻る)
(問い)導入時に各種セットアップなどをしてもらうことが可能ですか?
(答え)プロフェッショナルドクターはWindows上のソフトですので、ご自分でインストールなどは簡単にできますが、あらかじめハードやLANの設定・従業員の操作方法の教育などを行う有償サービスを開始しました。詳しくはお問い合わせください。
(戻る)
(問い)価格はいくらですか?
(答え)診療所用外来版で85万円です(4端末インストール可能・税別)
4端末以上にインストールする場合や、その他の版については詳しい資料をご請求ください。
(戻る)
(問い)メンテナンスのコストは?
(答え)メンテナンスのコストというのはソフトのメンテナンス料のことでしょうか?
プロフェッショナルドクターは医療機関の不必要なコストを削減するために開発されたソフトです。したがって、販売代理店などと特別な契約をしない限り、プロフェッショナルドクターには定期的なメンテナンス料は必要ありません。保険点数が改定になったときにマスターファイルの料金として1万円程度、制度の改定などでバージョンアップしたときに5万円程度でバージョンアップし、いつまでも使っていくことができます。いずれも希望者のみで、ご自分で改造して制度の改定に対応しているドクターもいらっしゃいます。
MyProdocでは導入価格は低コストですが、月額2万円のメンテナンス料がかります。
(戻る)
(問い)詳しい資料はありますか?
(答え)詳しい資料やパンフレットを用意していますのでお申し込みください。
(戻る)
(問い)自分としては開業時に何か新しいことをしたいので電子カルテを使ってみたいが、周りの人間はレセコンにしたらどうかというので迷っているのですが・・・。
(答え)現在電子カルテユーザーは爆発的に増加しています。新規開業の先生で特に若い先生は電子カルテを導入することが今やまったく普通のことになっています。レセコンが登場したのは10年以上前で、その間パソコンの世界では革命的な変化が連続しておきています。医療の世界にも影響が及ぶのは当然のことです。4年前に先駆的に登場したプロフェッショナルドクターも次の段階はLinux上のSQLベースのデータベースに対応した大病院用電子カルテシステムを登場させることになります。電子カルテはプロフェッショナルドクターが当初誕生したときと同じように、レセコンのような単なる医事ソフトではなく、薬剤情報データベース・診断学を含めた医学的情報をカバーする方向へとますます発展して進むことでしょう。もはや現在
ではこのような段階ですのでレセコンか電子カルテかという比較は成り立ちません。
ご自分が今後の診療でパソコンを有効に使用できるかどうかで決定されることが必要ではないでしょうか。
あるいはもう一つの判断基準として、院内LANを設置することが今後必要という判断であれば、電子カルテがよいでしょうし、院内LANの必要性はないということであればレセコンで充分だと思います。
(戻る)
(問い)カスタマイズできるそうですが、言語を知らないといけませんか?
(答え)そのような事はありませんが、
やりたい事に応じて必要な知識はことなります。
しかし、ソフトを立ち上げ、ファイルを開き、ソフトを終了する、あるいはファイルをコピーするなどパソコンを使用する上で当然知っておかなければならない事はあります。
プロフェッショナルドクターは診療データを後日利用できるようにし、かつ同じデータからレセプトなども出力したいというコンセプトで作られたものです。
また医療機関の業務スタイルもいろいろですので自院のスタイルに合った内容を追加したいときには自由にできるようにソースを変更できるようにしています。
たとえば自院の診療圏を知りたいときは適当なクエリーを作成できれば、患者名簿の住所などを出力して求めるデータを表示させる事もできるでしょう。
プロフェッショナルドクターは以下のような方をユーザーとして想定しています。
①前回と同じ処方箋を毎回書かなければならないような作業の無駄を無くすために以前のデータを利用したいと考えておられる方。
②データの重複入力(カルテに書いてレセコンにも入力)をなくしたいと考えておられる方。
③自分でカスタマイズして自分だけのソフトにしてみたい方。
そのために電子カルテに入力したデータをそのままレセプトに出力する事のできるシステムを、ソースを自由に変更できるようにして提供しています。
③のようなご希望を突き詰めていきますと、制度の改定にも自分で対処するというところまでいきます。
実際、プロフェッショナルドクターの販売当初はそのような先生がおられて、完全に制度の変更にもご自分で対処されています。
プロフェッショナルドクターの販売はそのようなことができるように、という目的を持って始まりました。
カスタマイズの原則は
①自分でできる範囲の事だけをする
②自分でできない事を他人に依頼しない
③カスタマイズした結果について自分で責任を負う
ということです。
プロフェッショナルドクターは最初から企業として数を売り、徹底的に営利を図るという目的で販売されているソフトではありません。完全に営利を図るのであれば、ソフトとしては別のあり方があります。
プロフェッショナルドクターは約5年前から販売をしていますが、最近電子カルテに順風が吹き始め、ユーザー層が拡大しています。
そのため従来のレセコンのようなサービスを期待される方も出てきました。これは困った事だと考えています。レセコンのようなサービスを期待されるのであればそれなりの費用がかかることを当然覚悟する必要があります。
いろいろな電子カルテソフトが出てきましたのでオプションが増えたという事はよい事で、今後はすみわけという事にもなるでしょう。
その中でプロフェッショナルドクターは上記のような希望をもつユーザー層を想定するという事は変わりません。
現在いろいろなソフトの中からどれにしようか迷っておられる場合は次のようにアドバイスいたします。
*医事システムを安くあげたいだけだから、データは3ヶ月だけあればいいという場合はレセコンあるいは医事機能に特化したソフトをお勧めします。
*自分で改造するのは面倒で、する気もないので最初からカスタマイズしてほしいという場合。カスタマイズするという事は特別発注という事ですから、それなりの費用もかかりますし、制度の改定にあわせて継続した特別のメンテナンスも必要です。(プログラマーは約80万円/人月の費用がかかります)
プロフェッショナルドクターは会社としてそのような人材が多数必要な業務形態を取っておりませんので、最初からそのような事が可能な他のソフトがあればそれをお勧めします。あるいはプロフェッショナルドクターのようなパッケージソフトを購入しないで、大病院がシステムを発注するように
自分で1からソフト会社に電子カルテの開発を依頼する道もあります。
*自分ではほとんど何もできないから徹底的に面倒を見てほしいという場合は、製薬会社やレセコン会社が販売するようなシステムを導入される方がよいでしょう。歯科用ではそのようなハードを含めたシステムがあるようです。
(戻る)
(問い)プロフェッショナルドクターを購入する方法を知りたいのですが。
(答え)
プロフェッショナルドクターはTEL/FAX/EーMailで詳しい資料・申し込み用紙を請求してください。お申し込みの場合はFAXで申し込み用紙をご請求の上、申し込み用紙に必要事項を記入しFAX・郵送にてお送りください。
プロフェッショナルドクターはお申し込みから1週間程度で着きます。
ププロフェッショナルドクターは中間マージンを排除するためにドクターもしくは医療機関への販売のみをいたしていますので医療機関やドクター以外の会社などが購入することはできません。
また医師同士の相互扶助を実践する会社ですから
医療機関やドクター以外の、会社関係などからの引き合いには応じておりませんのでご了承ください。
プロフェッショナルドクターの導入を検討される際に、ノーバメデイコや販売代理店以外のソフトハウス・パソコン販売店などの第三者を介して間接的に資料を請求されたり、購入しようとされる先生もいらっしゃいますが、プロフェッショナルドクターはドクターもしくは医療機関への直接販売のみをいたしておりますので、ノーバメデイコまたはノーバメデイコの販売代理店(福岡市:井原リアールエステイトメデイカル事業部)以外の第3者から資料を手に入れたり商品を購入することはできません。
必ずドクターまたは医療機関から直接ノーバメデイコやノーバメデイコの販売代理店へお問い合わせ、お申し込みください。
(戻る)
資料請求・申込先:〒060-0001札幌市中央区北1条西4丁目3-27 札幌北1条駅前通りビル5F
(株)ノーバメデイコ
電算医療事務センター
TEL:011-261-6305
FAX:011-61-6306
製品のラインナップ
資料請求
ホームページに戻る
![]()